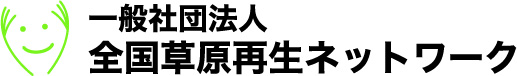全国草原再生ネットワークでは、各地の自治体が主体となって開催する「全国草原サミット・シンポジウム」を継続的にサポートしています。
第14回全国草原サミット・シンポジウム
テーマ つなげよう茅場が育んだ技術と命
開催自治体 長野県 小谷村
開催日程 2024年10月4日・5日
サミット参加自治体
- 大分県 竹田市
- 大分県 九重町
- 熊本県 西原村
- 島根県 大田市
- 鳥取県 江府町
- 広島県 安芸太田町
- 広島県 北広島町
- 兵庫県 神河町
- 岐阜県 白川村
- 静岡県 東伊豆町
- 長野県 白馬村
- 長野県 小谷村
プログラム
第14回全国草原シンポジウム
- 基調講演:カリヤスを刈る、葺く、雪国に暮らす知恵を探る(安藤邦廣氏・松澤敬夫氏)
- 研究報告:茅を育て、文化を守り伝える草原~信州小谷村、牧の入茅場から~(井田秀行氏)
- 分科会
- 第1分科会:草原の生物多様性~維持される仕組みに着目して~
- コーディネーター:井田秀行氏
- 発表者:高橋栞氏
- 第2分科会:茅刈りと茅葺きを未来につなぐ
- コーディネーター:上野弥智代氏
- 発表者:松澤朋典氏
- 第3分科会:草原の管理技術を学び伝える
- コーディネーター:武生雅明氏
- 発表者:栗田優氏・荻澤隆氏
- 第4分科会:草原資源を地域に生かし、次世代につなぐ
- コーディネーター:町田怜子氏
- 発表者:小谷中学校3年生
- 第1分科会:草原の生物多様性~維持される仕組みに着目して~
- 全体会・各分科会からの報告(コーディネーター:高橋佳孝氏)
現地見学会
- 牧の入り茅場(解説:井田秀行氏・実演田原重男氏・中村英子氏)
- 雨中ショクの茅場(解説:武生雅明氏・荻澤隆氏)
- 旧千國家住宅(牛方宿)(解説・実演:松澤朋典氏)
第14回全国草原サミット
- あいさつ
- 活動報告と問題提起、意見交換
- 前回全国草原サミットの報告(静岡県東伊豆副町長 鈴木嘉久氏)
- シンポジウムからの報告(問題提起:高橋佳孝氏)
- 各自治体の草原の課題
- 「未来に残したい草原100選事業」について
- 次回開催地の紹介
- 第14回全国草原サミット宣言採択
報告書
第13回 全国草原サミット・シンポジウム in 東伊豆
テーマ 未来へつなごう!壮大な海すすきの草原
開催自治体 静岡県 東伊豆町
開催日程 2021年
サミット参加自治体
- 兵庫県 新温泉町
- 宮崎県 串間市
- 宮崎県 川南町
- 岡山県 真庭市
- 島根県 大田市
- 広島県 北広島町
- 熊本県 南阿蘇村
- 熊本県 高森町
プログラム
第13回全国草原サミット・シンポジウム実行委員長(開催地)あいさつ
第13回全国草原シンポジウム
- 基調講演:草原をとりまく里が教えてくれる、持続可能な社会の未来像(白川勝信氏)
- パネルディスカッション「細野高原の活用と保全から、SDGsを理解する」
- コーディネーター 白川勝信氏
- パネリスト 太田長八氏、高橋佳孝氏、山田賢一氏、石島専吉氏
- 分科会
- 東伊豆会場:「利用・保全・継承」
- 阿蘇会場:「阿蘇草原再生、新たなステージへ 〜草原の恵みを守るための仕組みづくり〜」
- 蒜山会場:「人と自然の関係性の再生を目指して」
- 全体会
- 各分科会からの報告
- オンライン見学会
- 視察、オンライン見学会後の感想
第13回全国草原サミット
- 開催地あいさつ
- 活動報告と問題提起、意見交換
- 前回全国草原サミットの報告/日髙昭彦氏(宮崎県川南町長)
- シンポジウムからの報告、問題提起/高橋佳孝(全国草原再生ネットワーク代表理事)
- 各自治体の取組と課題
- 「未来に残したい草原100選事業」について
- 第13回全国草原サミット宣言採択
第12回 全国草原サミット・シンポジウム in 串間・川南
テーマ 黒潮洗う野生馬の草原とトロントロンが育む湿原
開催自治体 宮崎県 串間市・川南町
開催日程 2018年
サミット参加自治体
- 兵庫県 新温泉町
- 兵庫県 神河町
- 大分県 九重町
- 宮崎県 串間市
- 宮崎県 川南町
- 宮崎県 新富町
- 宮崎県 高鍋町
- 山口県 美祢市
- 熊本県 南小国町
- 群馬県 みなかみ町
- 長野県 小谷村
- 静岡県 東伊豆町
プログラム
第12回全国草原シンポジウム
- 実行委員会挨拶
- 開催地挨拶
- 来賓祝辞
- 基調講演Ⅰ:野焼きが育てた日本文化〜茅・屋根・信仰〜(永松 敦)
- 基調講演Ⅱ:宮崎の草原湿原と植物多様性の現状」(南谷 忠志)
- 分科会
- 第1分科会:「地域の宝」の草原・湿原を守るには?(西脇 亜也)
- 第2分科会:草原環境と持続可能な観光活用(田上 俊光)
- 第3分科会:茅と人々の暮らし(永松 敦)
- 第4分科会:保全技術の継承と安全対策(山内 康二)
- 全体会
- 各分科会からの報告
現地見学会
- 概要報告
- 調査研究報告:「川南湿原植物群落ホシクサ類の調査報告」(宮本 太)
湿原シンポジウム
- 実行委員会挨拶
- 開催地挨拶
- 来賓祝辞
- 講演:草原の秘密:野草堆肥の活用で安全・安心・高品質の農産物を!(染谷 孝)
- 事例発表1:川南湿原の保全活動について(松浦 勝次郎)
- 事例発表2:北川湿原の保全活動について(安藤 俊則)
- 事例発表3:和石地区の保全活動について(前田 律雄)
第12回全国草原サミット
- 来賓祝辞
- 活動報告と問題提起、意見交換
- 前回全国草原サミットの報告/西村 銀三(兵庫県新温泉町長)
- シンポジウムからの報告と問題提起/高橋 佳孝(全国草原再生ネットワーク会長)
- 各自治体の取組と課題
- ディスカッション
- 第12回全国草原サミット宣言採択
第12回 全国草原サミット in 串間・川南
今回の串間・川南での開催で12回目となる全国草原サミット・シンポジウムは、全国各地の草原の現状と課題に関して議論を深めながら、草原を有する自治体や地元住民、NPOなどが手を携え、連携と交流を図ることを目的に全国各地で開催されてきました。
その結果、前回開催の新温泉町では、「全国草原100選」の選定や「全国草原自治体ネットワーク」の設立が宣言されるなど、自治体の役割がより一層重要になり、草原保全活動は新たな局面を迎えつつあります。
今回、串間市で開催された全国草原シンポジウムにおいて、火入れや茅葺き屋根、牧の伝承における人々の知恵が草原維持のために重要であること、草原の持つ経済価値の評価も不可欠であること、「地域の宝」である草原・湿原を保全するには、稀少動植物、水源涵養、野草資源などの様々な「恵み」の価値を表有することが重要であることを確認しました。
第12回全国草原サミットでは、過去11回のサミットと今回のシンポジウムの成果を受けて、草原をめぐる今日的な問題について議論を行い、次の点について意見の一致をみました。
ここに”串間・川南宣言”を採択し、これまで以上に各自治体、諸団体との連携強化を図るとともに、その実現に向かって行動していきます。
串間・川南宣言
一、湿原を含む草原がもたらす様々な「恵み」を今後も享受するために、担い手の確保や保全活動を積極的に支援します。
一、草原管理の技術を次世代に引き継ぎながら、新たな技術やシステムを活用し、安全管理体制を構築します。
一、草原の大切さと公益的価値を広く国民にアピールするため、関係機関と連携しながら親しみやすい「全国草原100選」の選定を進めます。
一、全国の草原を有する自治体が情報を共有し、新たな保全対策に向けて連携して行動していくための「全国草原自治体ネットワーク(全国草原の里市町村連絡協議会)」の活動をより積極的に拡大、強化します。
以上宣言する。
平成30年5月14日
報告書
第11回全国草原サミット・シンポジウム In 上山高原
テーマ 人と草原 イヌワシが舞い 但馬牛があそぶ
開催自治体 兵庫県 新温泉町
開催日程 2016年
サミット参加自治体
- 兵庫県 新温泉町
- 兵庫県 朝来市
- 兵庫県 神河町
- 兵庫県 豊岡市
- 兵庫県 香美町
- 宮崎県 串間市
- 宮崎県 川南町
- 島根県 大田市
- 広島県 北広島町
- 熊本県 産山村
- 阿蘇市 町村会
- 鳥取県 岩美町
プログラム
第11回全国草原シンポジウム
- 基調講演「草原の再生と生物多様性」
- 実践報告
- 上山高原と人の歩みそして再生へ
- ススキ再資源化の取り組み~芸北茅プロジェクト~
- 野草堆肥における善玉菌のすばらしい世界
- 分科会
- 第1分科会:ジオパーク活動と草原
- 第2分科会:地域の草原を維持する仕組みづくり
- 第3分科会:草資源の農業・畜産への利用方法について
- 第4分科会:茅葺き文化の継承のための茅場の保存・再生
- 全体討論会
- 分科会からの報告とパネルディスカッション
- 「第10回全国草原シンポジウム宣言」の採択
第11回全国草原サミット
- 活動報告と問題提起・意見交換
- 前回全国草原サミットの報告
- シンポジウムからの報告と問題提起
- 各自治体の取り組みと課題
- 全国草原自治体ネットワークの設立について
- 「第11回全国草原サミット宣言」採択
オプショナルツアー
現地見学会~上山高原~
第11回全国草原サミットin上山高原
第11回全国草原サミットの舞台である上山高原は、周辺集落の人々にとって、田畑の土作り、和牛放牧や焼き畑、すすきは飼料、茅葺き屋根等に利用され、生活の一部として維持されてきました。また、地元の子どもたちは毎年上山登山を行い、貴重な教育の場でもありました。
しかしながら、かつて生活に欠かせなかった草原は、利用価値を失い、次々に放棄されてきました。その結果、イヌワシをはじめとする草原がもつ生物多様性に悪影響を与えています。また、麓の集落では獣害がひどくなり農作物づくりに弊害が生じています。これらは、全国各地の草原が抱える共通の課題です。
今回のテーマは「人と草原イヌワシが舞い但馬牛があそぶ」。
そこで、この豊かな草原の経済的な価値を再評価し、公益的な役割も確認しつつ草原の維持、保全並びに再生を支援していきます。また、そのためにも全国の草原を有する自治体及び住民が強固なネットワークを構築することが重要です。
草原を維持する新たな仕組みなどを共有し、次世代へと引きついでいくために、次のことを宣言します。
上山高原宣言
一、草原のなりたちから、社会的、公益的な価値を見つめ直し、交流事業を活用しながら、イヌワシを象徴とする生物多様性の維持のため自然環境の保全及び草原再生に向けた取組みを支援します。
一、農業や畜産などへの草資源の利用はもとより、ジオパーク活動等の新しい視点や枠組みを通じて、草原の有する良好な自然資源を教育、文化、観光、産業振興に利活用できる社会環境を整備します。
一、草原の大切さと公益的価値を広く国民にアピールするため、関係機関と連携しながら親しみやすい「全国草原100選」を選定していきます。
一、全国の草原を有する自治体が情報を共有し、新たな保全対策に向けて連携して行動していくために「全国草原自治体ネットワーク」を設立します。
平成28年10月17日
報告書
第10回 全国草原サミット・シンポジウム in 阿蘇
テーマ 守りつなごう草原の恵み!おとなも子どもも!
開催自治体 熊本県阿蘇市
開催日程 2014年
サミット参加自治体
- 山口県 美祢市
- 島根県 大田市
- 熊本県
- 熊本県 南小国町
- 熊本県 南阿蘇村
- 熊本県 小国町
- 熊本県 山都町
- 熊本県 産山村
- 熊本県 西原村
- 熊本県 阿蘇市
- 熊本県 高森町
- 群馬県 みなかみ町
- 阿蘇市町村会
プログラム
第10回全国草原シンポジウム
- 基調講演「草原が持つ公益的機能と経済的価値について」
- 事例報告
- 草原プロジェクト 阿蘇の草原文化を未来へ
- 世界農業遺産としての茶草場草地における茶生産と生物多様性
- 秋吉台の草原を次世代へー観光と保全の両立を目指してー
- 分科会
- 第1分科会:草原の公益的機能と経済的価値についてー本当に知っていますか?草原の恵みー
- 第2分科会:草原を地域の宝として輝かせる
- 第3分科会:幅広い市民運動としての草原保全活動と地元との連携
- 第4分科会:火入れの安全性確保について
- 第5分科会:第2回全国子ども草原サミット
- 全体討論会
- 分科会からの報告とパネルディスカッション
- 「第10回全国草原シンポジウム宣言」の採択
第10回全国草原サミット
- 全国草原サミット
- 「第10回全国草原サミット宣言」の採択
オプショナルツアー
- 現地見学会~草千里・南阿蘇・北外輪~
第10回全国草原サミットin阿蘇
全国には200カ所以上の草原が点在し、その四季折々の個性ある草原風景は訪れる人の心をやさしく包み込んでくれます。
草原が持つ生物多様性、特に希少動植物は生きるものにとってかけがえのない宝です。
しかしながら、今少子高齢化の現実に向き合い、農林畜産業などの後継者は減少の一途を辿り、地方は益々過疎化が進み、草原の維持、保全も年々厳しくなり地域住民だけでは、とうてい守り続けることが困難な状況になっている。
ここに、我々市町村長が、この豊かな草原の魅力と公益的な役割や価値について、広く国民にアピールし、これからの草原の維持、保全並びに再生を進めるため、全国の自治体が手を握り情報を共有しながら、新たな保全対策など、その実現に向けて具体的に行動していく必要がある。
阿蘇宣言
一、地元との交流人口拡大を図り、草原への理解と協力を得ながら、維持・保全のため防火帯づくりや野焼き作業の安全強化を行い、草原再生に取り組みます。
一、草原の重要性を次世代へ繋ぐため、草原の持つ魅力と役割を発信し、草原学習や体験学習を通じた教育の振興を進めます。
一、草原の維持・保全のため、地域資源を活かした特産品等の開発や販売促進など農林畜産業の振興と草原景観を活かした地域活性化に取り組んでいきます。
一、草原の重要性と公益的価値を広く国民にアピールしていくため、千年後も残したい日本の風景「草原100選」の制定に向け、関係機関に対し要望を行います。
一、自治体の連携強化のため全国組織の推進と充実化を図ります。
平成26年11月24日
報告書
第9回 全国草原サミット・シンポジウム in みなかみ
テーマ 〜川でつながる草原の恵み〜 流域コモンズで分かち合う、水源地域の豊かな自然と暮らし
開催自治体 群馬県 みなかみ町
開催日程 2012年
サミット参加自治体
- 島根県 大田市
- 広島県 北広島町
- 熊本県 西原村
- 群馬県 みなかみ町
- 群馬県 川場村
- 群馬県 昭和村
- 群馬県 沼田市
- 群馬県 片品村
- 茨城県 取手市
プログラム
全国草原シンポジウム
- 基調講演「里山における人の営みが、生物多様な環境を維持する」
- 各地の実践報告
- 乙女高原
- 阿蘇
- みなかみ町上ノ原
- 分科会
- 第1分科会:生態系サービスの見える化
- 第2分科会:草資源(茅)の多面的な利用とこれからの茅葺き
- 第3分科会:流域コモンズによる生物多様性保全と価値評価
- 第4分科会:草原と観光(ニューツーリズム)
- 全体討論会
第9回全国草原サミット
- 草原サミットの趣旨説明
- 前回草原サミットの報告
- 草原シンポジウムからの報告及び問題提起
- 各自治体における取り組み状況・ディスカッション
- 茨城県 取手市
- 群馬県 沼田市
- 群馬県 片品村
- 群馬県 川場村
- 群馬県 昭和村
- 島根県 大田市
- 熊本県阿蘇郡 西原村
- ディスカッションまとめ
- 全国草原サミット宣言
現地見学会
- 見学コース:上ノ原「入会の森」見学〜藤原ダムサイト〜諏訪神社〜雲越家住宅
- 茅刈り体験コース:茅刈り講習会〜茅刈り
- 星空観察会
第9回全国草原サミットみなかみ宣言
春の野焼き、草をはむ牛、風にそよぐ草、秋の草もみじ、冬には一面の銀世界。四季折々に姿を変える草原は美しく、花や虫などさまざまないのちにあふれ、私たちを魅了してやみません。
かつて草を使うことで保たれてきた日本各地の草原も、時代の変化とともにあるものは放置され、またあるものは開発され、いつの間にかわずかになってしまいました。
残された草原も、地域の過疎化や高齢化が進み、このままでは管理をし続けることが難しくなっています。
草は、刈っても刈っても生えてくる頼もしい資源です。先人たちは、そうした草原の恵みを上手に活かす仕組みと知恵を育んできました。日本の「草の文化」です。しかしそれもまた失われようとしています。
草原に今日的な価値を見いだし、草原を活用し、守ろうという新しい動きもあります。バイオマスエネルギーや建築材、エコツーリズムや文化、環境学習の場、生物多様性保全の場など、地域づくりに活かす試みが各地で見られるようになりました。
草の文化を引き継ぎ、こうした新たな動きをよりいっそう進めるために私たちは、多くの人が草原を知り、理解を深める機械を提供してまいります。
また、草原を守り、草原の恵みをこれからも享受するために、草原にかかわって暮らす人やさまざまな取り組みを行う人の活動を支援することに最善を尽くします。
草原を持つ自治体だけでなく、都市部の自治体も協力・恊働して草原にかかわり、その恵みを多くの人々で分かち合い、支え合うことを目指します。
そのためには自治体同士が連携を深め、首長をはじめ地域住民が交流し、情報交換を行うことが重要です。現代まで残る貴重な草原をこれ以上失うことなく、美しい姿で後世に引き継ぐために、今後も私たちは交流を継続し、全国の草原を保全・活用する取り組みを続けることを、群馬県みなかみ町において宣言します。
平成24年10月29日
報告書
第8回 全国草原サミット・シンポジウム(芸北)
テーマ 〜草原を核とした豊かな里づくり〜 多様な人と生き物が集う新田園空間
開催自治体 広島県 北広島町
開催日程 2009年
サミット参加自治体
- 大分県 九重町
- 島根県 大田市
- 広島県 北広島町
- 広島県 安芸太田町
- 阿蘇市町村会
- 鳥取県 江府町
プログラム
第8回全国草原シンポジウム
- 基調講演「コウノトリと共に生きる〜豊岡の挑戦〜」
- 各地からの実践報告
- 上ノ原 入会の森(群馬県 みなかみ町)
- 坊ガツル・飯田高原(大分県 九重町)
- 八幡高原(広島県 北広島町)
- 分科会
- 第1分科会:全国こども草原サミット
- 第2分科会:西中国山地の魅力 ー登山と草原ー
- 第3分科会:草原と暮らす、私たちの未来
- サテライト分科会:草原の持続可能な利用と生物多様性
- 第8回全国草原シンポジウム全体討論会
第8回全国草原サミット
全国草原サミット 北広島宣言
私たちの祖先が拓き、長い時間をかけて育んできた草原は、枯渇することのない資源として豊かな農村を支え、地域固有の財産とも言える独自の文化を育てました。その遺産は今日も変わることなく、バイオマスエネルギー、エコツーリズム、環境学習の場など、新たな利用も認められます。同時に草原は、極めて多様かつ特殊な生物群を育み、地域の生物多様性に深く貢献しています。美しく豊かな草原を守り続けている、地域の人々の知恵と弛みない営みこそ、私たちが誇りにすべきものであり、自然と共生した持続可能な社会を実現するものです。
一方、社会の変容は草原の利用低下を招き、多くの草原が森林へと変化しつつあります。加えて、農村では過疎化・高齢化が進み、草原の恵みを享受する仕組みは衰退の一途をたどっています。人々に豊かさをもたらし、生物多様性を支えてきた草原は、かつてない、危機的状況を迎えています。今こそ草原に関わる仕組みを再構築する時です。草原を保全し、その恩恵を将来にわたり享受できる社会の実現は、私たちに課せられた責務であり、農村の存続と発展、都市への恵みと豊かさをもたらすものであると考えます。
緊急の課題として、安全確保のために、火入れ時の体制を今一度見直し、伝統的な山焼きを継承するために必要な、可能な限りの支援方法を模索します。また、かけがえのない環境、危機的状況にある野生生物を保全するために、最善を尽くします。私たちは、地域社会と連携し、常に広く新しい視点を持ちながら、草原が持つ豊かな資源の利用について研究を続けることにより、草原の魅力を引き出し、故郷の魅力を高め、地域社会の担い手を育成します。
そして最も重要な事は、地域・ボランティア・利用者・研究者など、草原に関わる各主体との対話を継続することです。さらに、草原を有する市町村間の連携を含め、私たち首長同士が情報交換を続ける事だと考えます。私たちは、私たちに託された貴重な草原を、その価値を損なうことなく後生に引き継ぐために、今後も交流を深めながら、精励することを、北広島町において宣言します。
平成21年9月28日
報告書
全国草原シンポジウム’08 in 東伊豆
開催自治体 静岡県東 伊豆町
開催日程 2008年
第7回 全国草原サミット・シンポジウム in 大山・蒜山
テーマ 草原・牧野から大山・蒜山山麓の景観と環境保全を考える
開催自治体 岡山県真庭市
開催日程 2005年
第6回 全国草原シンポジウム・サミット in 霧ヶ峰
テーマ 心に残る草原を将来へ
開催自治体 長野県諏訪市
開催日程 2003年
サミット参加自治体
- 大分県 久住町(現 大分県 竹田市)
- 山口県 秋芳町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美東町(現 山口県 美祢市)
- 岡山県 真庭市
- 島根県 大田市
- 熊本県 阿蘇市
- 長野県 諏訪市
プログラム
プレイベント
第1部「霧ヶ峰の草原を体感する」白樺湖〜車山肩〜ゴマ石山〜園地
第2部「霧ヶ峰・自然とその歴史」霧ヶ峰ホテル
サミット・シンポジウム
- 基調講演「霧ヶ峰の今、昔」
- サミット・シンポジウムの趣旨発表「心に残る草原を将来へ」
- 全国草原サミット
- 各地の報告
- 島根県 大田市
- 岩手県 岩泉町
- 各地の報告
- シンポジウム分科会
- 第1分科会:「野火と草原の多面的な価値」
- 第2分科会:「住民の暮らし・産業と草原」
- 第3分科会:「来訪者と草原」
- シンポジウム分科会報告
- サミット宣言の採択
アフターイベント
- 霧ヶ峰たから探しツアー霧ヶ峰
報告書
第5回 全国草原シンポジウム・サミット in 阿蘇
テーマ 千年先に向けて今できること
開催自治体 熊本県久木野村(現 熊本県南阿蘇村)
開催日程 2002年
サミット参加自治体
- 熊本県 南小国町
- 熊本県 小国町
- 熊本県 浪野村(現 熊本県 阿蘇市)
- 熊本県 阿蘇町(現 熊本県 阿蘇市)
プログラム
秋吉台草原シンポジウム2001
- 基調講演「阿蘇草原の復活に向けて〜草原の多面的価値と新しい活用の方向〜」
- 各地の報告
- 島根県 大田市
- 岩手県 岩泉町
- 分科会
- 第1分科会:「草原の活用活性化への新たな取りくみ」
- 第2分科会:「このままじゃ牛もおらん 人もおらん!」
- 第3分科会:「パートナーシップによる草原の維持」
- 第4分科会:「考えよう!草原の様々な機能と利用」
- 第5分科会:「草原に関する行政の取り組み」
- 分科会報告会
第5回全国草原サミット
- 全国草原サミット
サミット宣言
阿蘇のカルデラを中心にして、その周囲を広大に取り巻く草原は、古代からの人々の営みにより大切に守られてきた大いなる財産です。また、阿蘇を訪れる人々にとっても日常に氾濫する騒音や喧騒から離れ、心地良い風を受けながら、自分自身を開放する癒やしの場にもなっています。
大自然の循環を受け持つ最上流の草原から育まれた雨水のひと粒ひと粒は、小さな沢から、やがては清冽な大河の流れとなって下流域を潤し、多くの恵みや生命の源にもなっているのです。
しかし、この草原も農畜産業の不振により、かつての輝きに満ちた緑の形成が失われ、草原の維持さえも危機的な状況が生まれようとしています。このような状況の中で徐々に草原が持つ多面的な価値が見直され、草原の再活用に対する取り組みや草原を維持するための新たな技術が芽生えてきました。残念ながら、肉食糧の中心となる牛肉は、BSE問題で全国的に大きなダメージを受けていますが、粗飼料多給型の「草原牛」は安全性の面で高い期待が寄せられており、「草原牛」の供給体制の強化は、減少する草原復活の国民的理解を得る契機として捉えることができます。
阿蘇の地で開催された第5回全国草原サミットは、過去4回の成果を振り返りながら、これをひとつの節目として位置づけ、今日の草原をめぐる様々な問題について、あらゆる角度から議論をおこない、次の点について意見の一致をみました。ここに“阿蘇宣言”を採択し、これまで以上に各自治体をはじめ、諸団体との連携を強化するとともに、その実現に向かって積極的にかつ具体的に行動していくものとします。
阿蘇宣言
草原の維持・存続には、草原を活用した農林畜産業、草地酪農の一層の振興を図るとともに、地産地消運動を繰り広げ、都市住民および消費者と農村の連携を強化しながら農村の活性化を進めます。
草原は、森林とともに水源滴養、環境浄化などの機能を有し、水系の源となっています。草原の維持は流域全体の問題でもあることをアピールし、財政的支援を含めた草原維持のための理解と協力に取り組みます。
野焼きの実施を担う牧野組合員等の高齢化や減少傾向が顕著になりはじめました。安全で効率的なモーモー輪地切りなどの実証試験の結果を踏まえながら、一層の省力化を図るとともに、輪地切り野焼きボランティアへの参加・協力・支援について都市住民の理解を深めます。
草原が持つ多面的な価値の評価について認識を深め、その重要性に着目して、景観の維持、希少動植物の保護管理体制の充実、さらに草原のツーリズム、バイオマス利用等への多面的利活用による草原活性化のために地域住民と都市住民および行政が連携し積極的な取り組みを展開します。
本サミットの存続ならびに自治体および諸団体の連携強化、また全国的な組織の拡充を図り、宣言内容の実現に全力であたります。
報告書
秋吉台草原シンポジウム2001/全国山焼きサミット in 秋吉台
テーマ 今、草原に必要なこと
開催自治体 山口県秋芳町(現 山口県美祢市)
開催日程 2001年
サミット参加自治体
- 北海道 小清水町
- 大分県 久住町(現 大分県 竹田市)
- 奈良県 曽爾村
- 宮崎県 串間市
- 山口県 秋芳町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美東町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美祢市
- 島根県 大田市
プログラム
秋吉台草原シンポジウム2001
- 基調講演
- 分科会
- 第1分科会:「観光と保全」ー事例発表ー
- 第2分科会:「生態系と保全」ー事例発表ー
- 第3分科会:「なりわいと保全」ー事例発表ー
- 第4分科会:「観光と保全」ー事例発表ー
- シンポジウム
- 特別講演「自然の中の動物たち〜ものまねと楽しいお話」
全国山焼きサミットin秋吉台
秋吉台宣言
今、草原景観は存亡の危機を迎えています。この危機は、そのまま草原に生きる虫や草花の絶滅の危機を招くと同時に、先人達が築いてきた草原文化を根底から揺るがそうとしています。農林業や畜産業の衰退によって、採草や放牧という利用目的が失われつつあるからです。草原景観の維持は、各地域共通の問題点です。
一方で、社会の進展と高度化によって、蝕まれ披露した心の癒しの場所として、美しい草原には多くの人々が訪れるようになりました。人々の健康と安らぎにとって、草原はかけがえのない場所となってきたのです。そこには観光、福祉、健康という新たな生業も育ちつつあります。
本日「秋吉台山焼きサミット」に集う自治体は、草原景観を「地域の宝」、「国民の財産」として維持保全していくことを話し合いました。また共に、「人々の癒しの草原」を管理保全する責務も認識しながら、運営上貧窮している実情も協議しました。今後は機会あるごとに、こうした実情を国や国民に訴えかけ、「国民の財産」、「地域の宝」として、援助と支援を要請しながら、草原景観の維持保全に一層の努力を傾注することを宣言いたします。
2001年2月17日
報告書
第3回 全国草原サミット 野焼きシンポジウム・イン・小清水
テーマ 草の言い分、花の言い分、人の言い分
開催自治体 北海道小清水町
開催日程 2000年
サミット参加自治体
- 北海道 女満別町(現 北海道大空町)
- 北海道 小清水町
- 北海道 斜里町
- 北海道 東藻琴村(現 北海道大空町)
- 北海道 津別町
- 北海道 清里町
- 北海道 網走市
- 北海道 美幌町
- 北海道 長沼町
- 大分県 久住町(現 大分県 竹田市)
- 山口県 秋芳町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美東町(現 山口県 美祢市)
- 島根県 大田市
プログラム
草原シンポジウム’97
- 基調講演
- 各地からの報告
- 小清水原生花園(北海道)
- 箱根町仙石原(神奈川県)
- ナイジェリア石像遺跡に及ぼす森林火災と野火の影響
- インドネシアの熱帯泥炭湿地の森林火災と消火活動
- シンポジウム
- 特別講演「自然の中の動物たち〜ものまねと楽しいお話」
第3回全国草原サミット
原生花園宣言
草原は多くの生命を育み、さまざまな野の贈り物を私たちにもたらします。
それは美しい景色とともに、豊かな生産を約束する場です。
草原は世界中で、古くから人々によって用いられ、保たれてきました。その保全と賢明な利用こそ、これからも引き続き守られなければなりません。
私たちは、第3回全国草原サミットを機会に、草原の重要性を改めて認識するとともに、これを私たちばかりでなく、草原を訪れたことのない人々たちにもの訴えたいと思います。
草原生態系の維持と活用に、その技術の伝承と、さらなる知恵と努力を集めることを期待して。
そして、本サミットを今後とも継続して、草原を有する自治体間の連携をより一層図ってまいります。
以上宣言します。
2000年6月24日
報告書
第2回 全国草原シンポジウム・サミット(大田)
テーマ 草原の意義と生業による維持保全管理
開催自治体 島根県大田市
開催日程 1997年
サミット参加自治体
- 北海道 小清水町
- 大分県 久住町(現 大分県 竹田市)
- 大阪府 河内長野市
- 山口県 秋芳町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美東町(現 山口県 美祢市)
- 島根県
- 島根県 大田市
- 島根県 温泉津町(現 島根県 大田市)
- 島根県 知夫村
- 島根県 西ノ島町
- 島根県 頓原町(現 島根県 飯南町)
- 群馬県 嬬恋村
プログラム
草原シンポジウム’97
- 基調講演
- 各地からの報告
- 兵庫県村岡町
- 大分県久住町
- 群馬県湯ノ丸
- 大阪府岩湧山
- 各地からの報告
- シンポジウム
第2回全国草原サミット
- 全国草原サミット
全国野焼きサミット 三瓶宣言
わが国の草原は、人為と自然の調和によってはぐくまれてきた貴重な自然遺産であると同時に、日本のふるさとの原風景として、次の世代に引き継いで行くべき大切な文化遺産である。
草原は、火入れと放牧、採草という、数百年以上に渡って繰り返されてきた農畜産の営みによって、形成されてきた。主に入会地として利用、管理されてきた草原は、近年、農村社会の変貌と農林畜産業の急激な衰退とにより荒廃の一途をたどっている。草原のみならず、今や、農村は森林も田畑も、同じ問題を抱えているが、草原はその変化が最も早く現れる点で、農村の荒廃の象徴でもある。
本サミットでは、こうした事態を憂い、対応するために、以下の点について、意見の一致を見た。この共通認識をここに三瓶宣言としてまとめ、農と命を尊ぶ全国の人たちに、理解と協力を求めるものである。
草原を守るためには、農林畜産業の振興が不可欠であるとの認識に立ち、農業者と都市の生活者が手を携えて、地域連体型の総合的自給運動を展開し、農村の活性化を図っていく。
草原を国民共有の土地(コモンランド)と位置づけ、住民と行政、および民間団体が協力して、草原の持続的な利用と管理の新しいシステムを創出し、実現していく。
草原及び里山の価値と、維持することの重要性について、広く啓発し、それらを保全していくために、農業、生態、制度など、多様な観点からの活動を呼びかけていく。
本サミットを今後も継続し、日本各地の草原を有する自治体間のネットワークを広げ、より一層の連携を図っていく。
1997年10月4日
報告書
第1回 全国野焼きシンポジウム・全国野焼きサミット(久住)
テーマ 野焼きボランティア参加の可能性と未来
開催自治体 大分県久住町(現 大分県竹田市)
開催日程 1995年
サミット参加自治体
- 北海道 小清水町
- 山口県 秋芳町(現 山口県 美祢市)
- 山口県 美東町(現 山口県 美祢市)
- 熊本県 一の宮町(現 熊本県 阿蘇市)
- 熊本県 南小国町
- 熊本県 産山村
- 熊本県 阿蘇町(現 熊本県 阿蘇市)
プログラム
久住高原野焼きシンポジウム
- 基調講演
- 各地からの報告
- 小清水原生花園(北海道)
- 三瓶山(島根県 大田市)
- 秋吉台(山口県)
- 阿蘇(熊本県)
- 座談会「草原の意義とその維持のための課題」
全国野焼きサミット
全国野焼きサミット 久住宣言
日本の草原は、放牧・採草・野焼きなどの人間の営みとの関わりの中で形成され、維持されてきた。美しい草原景観が評価され、国立公園、国定公園などに指定されている地域も多い。
しかし、近年、農村における過疎・高齢化・農畜産業の不振や変質、草原に対する無理解など草原をとりまく様々な環境の変化により、日本の草原は年々減少しつつある。
本サミットでは、今日の草原をめぐる諸問題について、地元自治体の立場から議論を行い、次の点について意見の一致をみた。
閉会にあたり、この共通認識を「久住宣言」としてまとめ、ここに宣言する。
本サミットを契機として、日本各地の草原を有する自治体間の交流の輪を広げ、連携を密にしていく。
草原の価値と草原を維持することの重要性について広く世論の理解を求めるため、共に行動していく。
絶滅しつつある日本の草原を維持していくための方策について、共に考えていく。
1995年3月4日